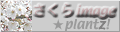 _
_
さくらの文学
花は桜木、人は武士
〜武士道と桜〜
|
■
花は桜木、人は武士 作文中 古来人々が美しすぎる桜の美にただならぬものは感じていたとしても それが社会的な広がりを持って死と結びついたのは どうも江戸時代の歌舞伎の演目、仮名手本忠臣蔵において 浅野内匠頭切腹の場での演出として桜が使われたことが大きいようです。 誰もの脳裏に「桜=死」が具体的なイメージとして刷り込まれたことでしょう。 さらには大石内蔵助に大阪商人天河屋義平の心意気を 「花は桜木、人は武士と申せども、いっかな武士にも及ばぬご所存。」 とも言わせています。 元禄の世では大衆の目には「美しく咲いていさぎよく死ぬ」という武士道は すでに様式と化していたことが透けて見えてきます。 (役名ではなく実際のモデルの名で記しました。) ■ 染井吉野の登場 このころ登場したソメイヨシノは山桜より花つきがよく、 またたくまに一斉に散ってしまう性質でそんな美意識に答えました。 幕末の志士たちが我が身を重ねた散る桜は すでに山桜ではなく染井吉野の方だったかもしれません。 さて、この今や桜の代名詞「染井吉野」ですが、 たしかに江戸彼岸と大島桜の交雑種であるのは間違いないようですが 実はなかなかやっかいな謎の桜なのです。 項をあらためた方がよさそうです。 ※この項、引用および管理人の推論で構成されていますのでこのあとも改訂が予想されます。 他への紹介はご注意ください。 070505 |
(infoseek web辞書より抜粋) 【仮名手本忠臣蔵・かなてほんちゅうしんぐら】 人形浄瑠璃の時代物。竹田出雲・三好松洛・並木千柳作。 1748年竹本座初演。通称「忠臣蔵」。 赤穂義士の仇討ち事件を題材としたもの。 時代を「太平記」の世界にとり、 塩谷(えんや)判官(浅野内匠頭(たくみのかみ)) の臣大星由良之助(大石内蔵助(くらのすけ))ら四十七士が 高師直(こうのもろなお)(吉良上野介(こうずけのすけ))を討つことを主筋に、 お軽・勘平(萱野三平)の恋と忠義などを副筋に脚色。 初演後すぐに歌舞伎にも移された。 人形浄瑠璃・歌舞伎の代表的演目で、 興行して不入りのことがないところから、 芝居の独参湯(どくじんとう)(起死回生の妙薬)と称せられる。 |
