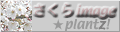 _
_
さくらの文学
特攻戦闘機「桜花」
〜そして、軍国の花〜
|
■
桜と軍国主義 作文中 「彼岸」からはずれますが、その桜の美にまとわりつく死の気配が この国の歴史におよぼした見落とせない負の足跡がありますね。 そうして武士道と重ね合わされた桜花は 軍国主義の中でゆがんだ大きな役割を持たされてしまいます。 桜は勇ましい死を鼓吹する道具、国粋イデオロギーの象徴、 つまり「軍国の花」「国華」「靖国の花」となり、 桜は桜本来の無垢な美くしさから離れてしまいました。 陸軍唱歌「歩兵の本領」 明治44 一、 万朶(ばんだ)の桜か襟の色 花は吉野に嵐吹く 大和男子(やまとおのこ)と生まれなば 散兵線の花と散れ 「同期の桜」 昭和19 一、 貴様と俺とは同期の桜 同じ兵学校の庭に咲く 咲いた花なら散るのは覚悟 見事散りましょ国のため 五、 貴様と俺とは同期の桜 離れ離れに散ろうとも 花の都の靖国神社 春の梢(こずえ)に咲いて会おう 「二輪の桜」(西条八十)が元 昭和13年、 君と僕とは二輪の桜 積んだ土のうの影に咲く どうせ花なら散らなきゃならぬ 見事散りましょ国のため 「積んだ土のうの影に咲く」「散らなきゃならぬ」「君と僕」という 否定的だったり軟弱な表現はしりぞけられます。 ■ 特攻戦闘機「桜花」 太平洋戦争末期の昭和19年、 大日本帝国海軍は一人乗りの自爆式戦闘機という、 それこそ空前絶後、とんでもない空飛ぶ特攻兵器を造り出しました。 そしてここでも桜は利用されるのです。 戦闘機はその使命を体現した「桜花(おうか)」と名づけられました。 歴戦の、または若いパイロットを瞬く間に失うという 末期的戦術をとりつくろう一方、自虐的命名とも言えます。 また、特攻機のパイロットが敵艦に体当たりすることを「散華」といいましたが、 もちろん「さくら花」が風に散っていく光景と二重写しになっています。 桜がこの国の花であることに異存はないでしょう。 しかしほんの半世紀前のこの桜にまつわる歴史もまた私たちは背負っていくのです。 この項、引用および管理人の推論で構成されていますのでこのあとも改訂が予想されます。 他への紹介はご注意ください。 070506 |
さんげ【散華】 (1)〔仏教) 仏を供養するために花をまき散らすこと。 特に法会(ほうえ)で、偈(げ)を唱えながら列をつくって歩き、 蓮の花びらの形をした紙をまき散らす法要。 (2)戦死を美化していう語。 「南海に散華した勇士」 (web大辞林) 都はるみの歌う「散華」に織り込まれた花(作詞 吉田旺) 櫻 れんぎょう 藤の花 芙蓉 すいれん 夾竹桃 野菊 りんどう 金木犀 桔梗 侘助 寒牡丹 歌詞はこう括られます。 燃えたぎる命 いのち懸けてまで 掴もうとした 未来(ゆめ)よいずこ……いずこへ せめて空に舞え 見果てぬ想いのせて あゝ海に降れ 散華の花弁(はなびら) |
