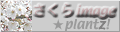 _
_
さくらの文学
桜に彼岸を見た人たち
〜西行法師〜
|
■
憑(つ)かれたように桜を詠んだ西行。その視線の先には・・ ねがはくは 花のしたにて 春死なん その如月の 望月のころ 「花」との対比でつい心地よく読み流してしまう「望月」ということばについて。 如月の望月(満月)の日、 つまり旧暦2月15日は 釈迦入滅の日という当時は周知だったろう特別の日と重なるようです。 西行がそれをふまえていたかどうかはわかりませんが しかし、西行という人が 「花(桜)と月(満月)」を並べて美しくまとめる言葉遊びで満足する人物でなさそうなことに思いをはせると この「望月」という言葉にも何か思いが託されているのではないかと考えてみたくなります。 (この項、検証はしていません。どこかで目にした引用と推論です。) 鎌倉時代は 里桜が作られ始めたと考えられている頃ですが 西行が歌う桜は普通に考えて山桜です。 江戸彼岸には遅いし もちろん染井吉野はありません。 桜の美しさの向こうに彼岸を想う感性、 和歌という定型に凝縮された壮絶な無常観。 日本人の琴線をふるわすもう一首。 桜が夢とうつつ、あちらとこちらをつなぐ触媒であることをとらえてみごとです。 春風の 花を散らすと 見る夢は さめても胸の さわぐなりけり 050609 |
西行(1118-1190) 平安末期から鎌倉初期。俗名、佐藤義清(のりきよ)。もと北面の武士。 23歳で出家。諸国を旅しすぐれた和歌を残す。 「新古今集」では最高の94首が入集。家集「山家集」など。 北面の武士(ほくめんのぶし) 11世紀末(平安後期)、白河上皇が院の護衛のために置いた武士集団のこと。 御所の北面を詰所としていたので、この名がついた。 藤原氏の本拠地が院の北側にあったため、北面に配置されたとされている。 後の平家台頭のきっかけとなった。 西行忌 2月16日 きさらぎ 【如月/衣更着/更衣】 陰暦二月の異名。新暦(太陽暦)では三月末。[季]春。 |
